「ベビーカステラ」と「東京ケーキ」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも屋台などで見かける球状の焼き菓子ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
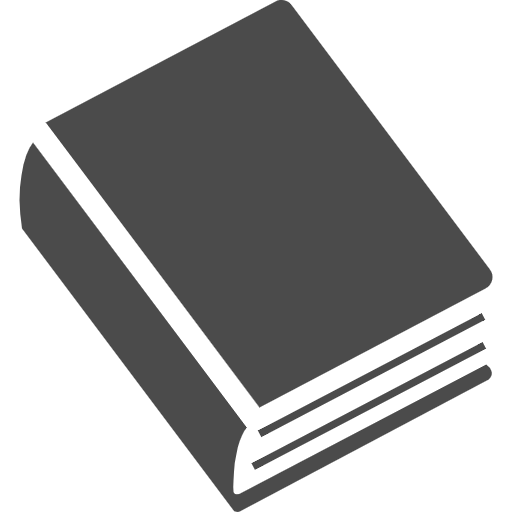
このページを読めば「ベビーカステラ」と「東京ケーキ」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
ベビーカステラの定義
「ベビーカステラ」は広辞苑に掲載がないためインターネットで調べてみたところ、ホットケーキやカステラに似た生地を楕円状の型に流し込んで焼いたお菓子であることがわかりました。
お祭りの出店などでよく売られており、家庭ではたこ焼き器を使用して作られる事もあります。
1918年に関西地方の露天組合である金城組が売り出したものが、ベビーカステラの発祥とされています。
「ベビーカステラ」という名前は「小さなカステラ」を意味する言葉で、昭和29年に三宝屋という老舗専門店によって名づけられました。

東京ケーキの定義
「東京ケーキ」も広辞苑に掲載がないためインターネットで調べてみたところ、「東京ケーキ」もベビーカステラとほぼ同じ材料と作り方で作られるお菓子であることがわかりました。
つまり東京ケーキとベビーカステラは同じものを指すのですが、東京ケーキという呼び名は実は愛媛県のみで使用されている言葉です。
なぜ愛媛なのに「東京」という名がついているかの確かな理由は不明でしたが、材料を東京から仕入れていたから、または東京への憧れがあったから、などという説もありました。
なお、ベビーカステラは地域ごとに様々な名前で呼ばれています。
- 松露焼き:姫路市
- 玉子焼き:神戸市
- チンチン焼き:関西地区
- 福玉焼き:明石市
- ピンス焼き:淡路島

つまり「ベビーカステラ」と「東京ケーキ」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- ベビーカステラは「生地を楕円状の型に流し込んで焼いたお菓子」
- 東京ケーキは「ベビーカステラと同じものだが、愛媛独自の呼び名」
となり、「ベビーカステラ」も「東京ケーキ」も同じ作り方のお菓子ですが、地域によって独自の呼び方があり、そのひとつが愛媛の「東京ケーキ」であるということが分かりました。
他にもケーキや菓子の違いについてまとめています。




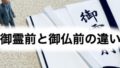
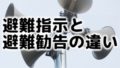
コメント