「じゃがいも」と「馬鈴薯」の違い、あなたは説明できますか?
どちらもスーパーなどでよく見かける見た目も味も似ている野菜ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
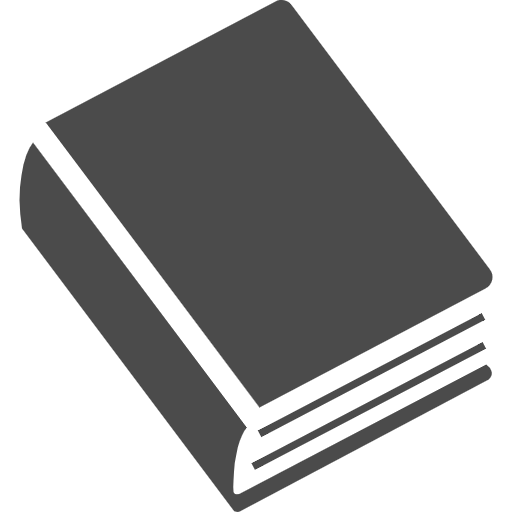
このページを読めば「じゃがいも」と「馬鈴薯」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
じゃがいもの定義
「じゃがいも」を広辞苑で調べると、
(「ジャガタラいも」の略。慶長年間、ジャカルタより渡来したからいう)ナス科の一年生作物。南米のアンデス高地の原産。塊茎は澱粉に富み、食用。また、澱粉・アルコールの原料、飼料用。男爵など多数の栽培品種がある。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「じゃがいも」はナス科の一年生の作物で多数の品種があり、食用としてだけでなく飼料用としても世界中で広く栽培されているイモであることが分かりました。
「じゃがいも」は江戸時代の16世紀末にオランダ人によってインドネシアのジャカルタを経由して日本に伝えられました。当初はジャカルタのいもなので「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、略されて現在は「じゃがいも」と呼ばれるようになっています。
「じゃがいも」には多くの品種があり、食用として多く出回っているのがメークインと男爵です。メークインは粘質で煮崩れしにくく、煮物などに向いています。一方、男爵は粉質でホクホクとした食感が特徴で、ポテトサラダやコロッケなどに向いています。

馬鈴薯の定義
「馬鈴薯」を広辞苑で調べると、
(とくに作物としていう)ジャガイモの別称。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「馬鈴薯」は「ばれいしょ」と読み、作物としてもじゃかいもの別の呼び名であることが分かりました。
「馬鈴薯」という呼び名は中国が由来といわれています。中国ではマメ科のホドイモのことを指し、馬の首に付ける鈴に似ていたことから「馬鈴薯」と名付けられました。
江戸時代後期の1808年、薬用植物学者の小野蘭山が「馬鈴薯がじゃがいもである」と解説したことから、「じゃがいも」を「馬鈴薯」とも呼ぶようになりました。

つまり「じゃがいも」と「馬鈴薯」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- じゃがいもは「ジャカルタからきたジャカルタいもの略称」
- 馬鈴薯は「中国からきたじゃがいもの別の呼び名」
となり、「じゃがいも」と「馬鈴薯」は呼び名が違うだけで、同じものを指すことが分かりました。農林水産省や農業協同組合などの行政・生産分野では「馬鈴薯」、学会や研究機関などでは「じゃがいも」と呼ばれることが多いようです。
男爵いもとメークインの違いはこちらでまとめています。





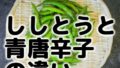

コメント