「木綿豆腐」と「島豆腐」の違い、あなたは説明できますか?
沖縄名物の島豆腐は、見た目がずっしりとしていて”大きな木綿豆腐”のようですが一体何が違うのでしょうか。
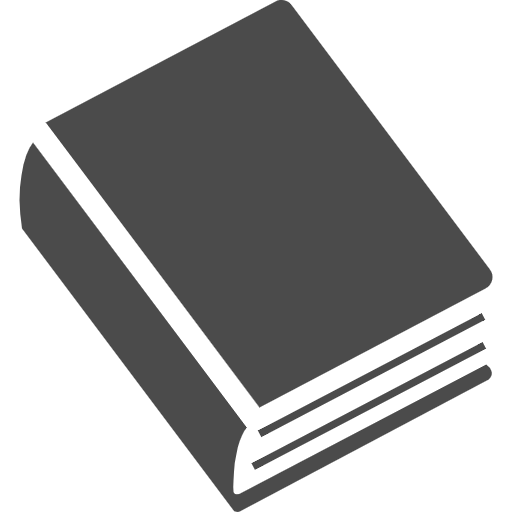
このページを読めば「木綿豆腐」と「島豆腐」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
木綿豆腐の定義
豆乳に凝固剤を加えて固め、上澄み液を除き成型した豆腐。型箱に敷く木綿の布目が表面につくからいう。
広辞苑 第七版 2923Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、木綿豆腐は1度固めた豆腐を、木綿の布を敷いた箱に入れて重しを乗せて水分を抜くため、水分の少ないしっかりとした豆腐となることが分かりました。
水分が少ない分、タンパク質などが豊富で大豆の味がしっかりと感じられるのが特徴です。
また、崩れにくく味が滲みやすいため、煮物などに向いています。

島豆腐の定義
「島豆腐」は広辞苑に掲載が無いためWikipedia等でリサーチしたところ、島豆腐は「沖縄豆腐」とも呼ばれる沖縄名物の豆腐であることが分かりました。
普通の豆腐は大豆を水につけて挽いた汁を煮てから濾す「煮とり製法」で作られるのに対し、島豆腐は濾してから煮る「生しぼり製法」で作るという違いがあります。
島豆腐はこの「低温で絞る」製法により大豆のエグみなどが取り除かれ、大豆の旨みが濃い美味しい豆腐となります。
島豆腐は一般の木綿豆腐の倍以上の大きさで販売されており、固く重いのが特徴です。
そのため、チャンプルーなどの炒め料理に使用してもあまり崩れません。
沖縄では普通のスーパーで、多くの島豆腐が販売されていますが、豆腐をメインとしたゴーヤチャンプルーや、豆腐に魚の塩漬けを乗せた”スクガラス豆腐”など、豆腐メインの料理が多いこともあり、この量が使いきれてしまうようです。

つまり「木綿豆腐」と「島豆腐」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 木綿豆腐は「大豆を水につけて挽いた汁を加熱後に濾す製法を用いる」
- 島豆腐は「大豆を水につけて挽いた汁を濾してから加熱するため、えぐみが無く大豆の味が濃くなる」
となり、大きさや重さのだけではなく、大きな違いは「製法」であることが分かりました。
島豆腐を一度食べると、普通の木綿豆腐では物足りなくなると言われるほどですので、「木綿豆腐と同じでしょ?」と思っている方は一度食べてみると良いかもしれません。
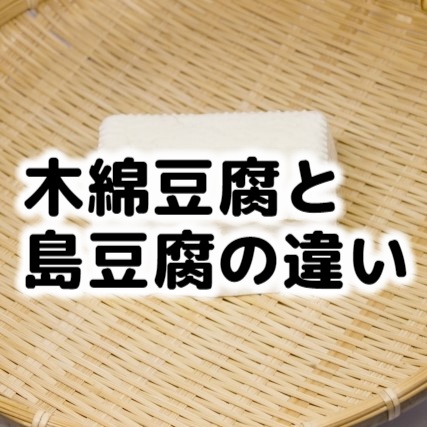



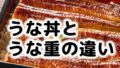

コメント