「三角州」と「扇状地」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも地形を表す言葉ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
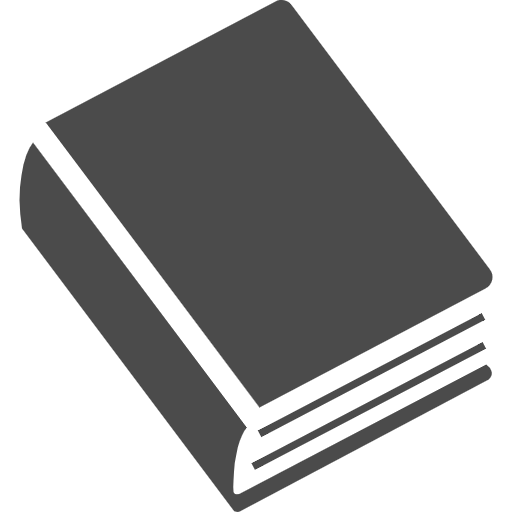
このページを読めば「三角州」と「扇状地」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
三角州の定義
「三角州」を広辞苑で調べると、
河水の運搬した土砂が、河口に沈積して生じたほぼ三角形の土地。デルタ。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「三角州」は河口に土砂が沈積して生じた三角形の土地、であることがわかりました。
三角州のほとんどは海面すれすれの水準にあるため、土地が低く湿気が多い他、こう配が緩やかといった傾向があります。
大河の場合は、河口に複数の三角州が形成されることもあり、それらをまとめてデルタや三角州と呼ぶこともあります。
また季節風が吹くアジアの河川は、一般に傾斜が急で流量も大きいため、土砂の運搬作用が大きく、河口に三角州が形成される場合が多いのが特徴です。

扇状地の定義
「扇状地」を広辞苑で調べると、
川が山地から平地へ流れる所にできる、下流に向かって扇状に拡がる地形。流れの勢いが急に緩やかになって砂礫を堆積した結果、形成される。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「扇状地」は山地と平地の間にできた扇状に広がる地形、ということがわかりました。
扇状地は、三角州と同じく河川によって運搬された土砂などが、山地間の谷底や平地にかけて堆積して平野となったものです。
名前の由来は、扇子(せんす)の形に似ているためで、扇状地の頂点を扇頂、末端を扇端、中央部を扇央と呼びます。
日本における扇状地は、江戸時代末期から明治にかけて開発が進められ、綿畑、桑畑、茶畑、麦畑、果樹園などに利用されてきました。

つまり「三角州」と「扇状地」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 三角州は「河口に土砂が沈積して生じた三角形の土地」
- 扇状地は「山地と平地の間にできた扇状に広がる地形」
となり、「三角州」は土地が低く湿気が多くこう配が緩やかな点が特徴で、「扇状地」は開発により果樹園などに利用されている、ということがわかりました。
山地と山脈の違いはこちらでまとめています。







コメント