「舞妓」と「芸姑」の「芸者」の違い、あなたは説明できますか?
いずれも芸を披露して観客を楽しませる人のことですが、それぞれに明確な違いはあるのでしょうか。
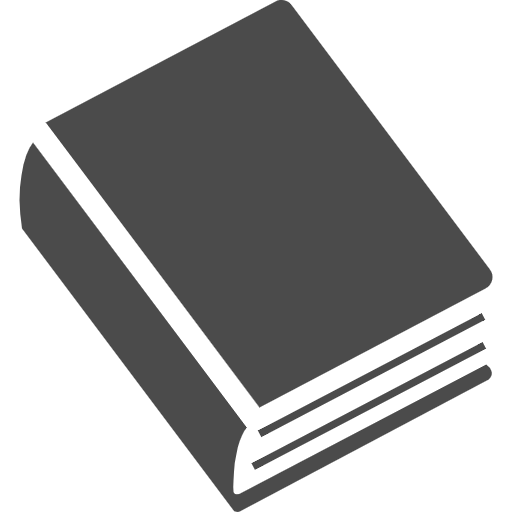
このページを読めば「舞妓」と「芸姑」と「芸者」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
舞妓の定義
「舞妓」を広辞苑で調べると、
舞を舞って酒宴の興を添える少女。おしゃく。はんぎょく。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「舞妓」は舞を舞って宴席を盛り上げる少女であることが分かりました。
「舞妓」は京都の五番街(上七軒、先斗町、宮川町、祇園甲部、祇園東)のお酒の席で歌や踊り、三味線などの芸を披露し観客を楽しませます。
「舞妓」になるには、保護者同伴で置屋の女将さんと面接を受け採用される必要があり、採用後は約一年間は見習いの仕込みさんとして修業をすることになります。また、「舞妓」には15歳から20歳までといった年齢制限があります。

芸姑の定義
「芸姑」は広辞苑に記載がないため同じ意味を持つ「芸妓(げいぎ)」を広辞苑で調べると、
酒宴の間をとりもち、歌・三味線・舞踊などで客を楽しませる女。芸者。芸子げいこ。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「芸姑」は歌や三味線などで宴席を盛り上げる女性であることが分かりました。
「芸姑」は客のお酌や話し相手もしますがメインの仕事は芸を披露することです。また、舞妓には20歳までといった年齢制限がありますが、「芸姑」は定年がなく一生続けることができます。


芸者の定義
「芸者」を広辞苑で調べると、
多芸な人。遊芸に巧みな人。芸達者。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「芸者」は芸達者な人を指すことが分かりました。
「芸者」は宴席で舞踊や音曲、鳴物などを披露して客をもてなす人を広義に指す言葉で、上で解説した舞妓や芸姑も含まれます。現代では「芸者」のなり手が減少傾向になりそれと同時に高齢化も進んでいます。

つまり「舞妓」と「芸姑」と「芸者」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 舞妓は「舞を舞って宴席を盛り上げる少女」
- 芸姑は「歌や三味線などで宴席を盛り上げる女性」
- 芸者は「芸達者な人を指す言葉」
となり、「舞妓」は宴席を盛り上げる15歳から20歳までの少女であるのに対し、「芸姑」は定年のない宴席を盛り上げる女性であり、「芸者」は宴席を盛り上げる人全般を指す言葉であることが分かりました。
「料亭と割烹の違い」についてもまとめています。






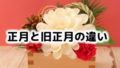
コメント