「青」と「蒼」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも色を意味しており、口に出すと同じ「あお」という言葉ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
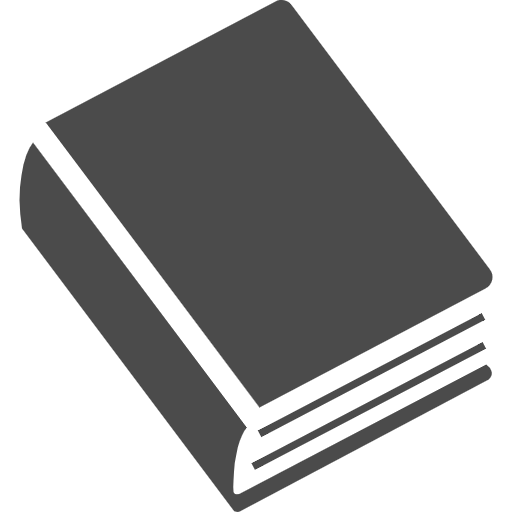
このページを読めば「青」と「蒼」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
青の定義
「青」を広辞苑で調べると、
(一説に、古代日本語では、固有の色名としては「あか」「くろ」「しろ」「あお」があるのみで、それは明・暗・顕・漠を原義とするという。本来は灰色がかった白色をいうらしい)
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
七色の一つ。また、三原色の一つ。晴れた空のような色
とのことで、「青」はあお色の総称で、特に晴れた空のような色を表すことがわかりました。
現代ではさわやかなイメージのある色ですが、昔は灰色っぽい色の意味があったようです。
青系の日本の伝統色は69種類に分かれます。淡い色には水色や空色など、濃い色には藍色、瑠璃色、紺色などがあります。
藍鼠色や青鈍色などは、ぱっと見た感じでは灰色に思えますが、昔は灰色がかった色を指していたということであれば納得がいくかもしれません。

蒼の定義
「蒼」は広辞苑に掲載がないため「青い・蒼い」で調べると、
青色である。緑・藍・蒼・碧に通じていう。青白い。一般には「青」。くすんだあお色や血の気のないあお色には「蒼」、浅緑色から濃青緑色では「碧」も使う。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「蒼」はあおのなかでもくすんでいるような色の場合に使用することがわかりました。また、緑がかったあおの場合は「碧」となるようです。
「蒼」という漢字は、草木が生い茂る様子を表す「鬱蒼」という言葉に使われることからも、あまり派手ではない色のイメージがあります。
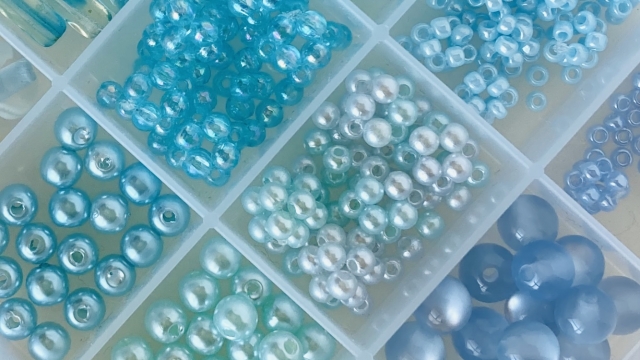
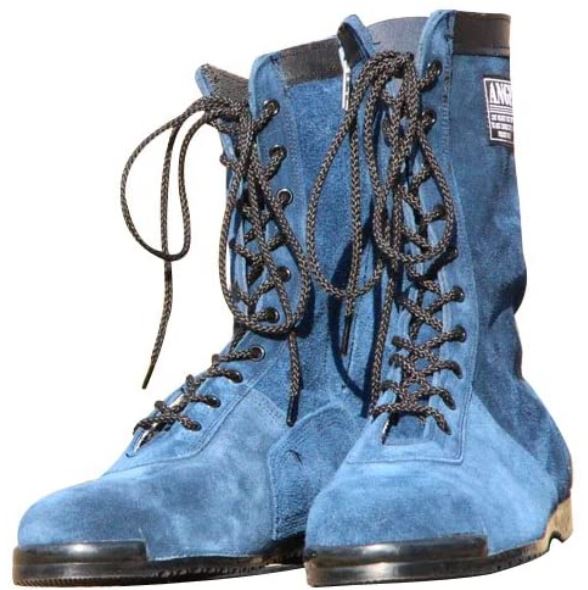
つまり「青」と「蒼」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 青は「様々なあお色の総称、晴れた空のような色を表す」
- 蒼は「くすんだあお色」
となり、「青」は数多く存在するあお色のなかでも澄んだ色を表す場合に使用されるのに対し、「蒼」はくすんだ色を表す場合に使用されることが分かりました。



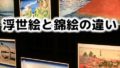

コメント