「サラミ」と「カルパス」の違い、あなたは説明できますか?
サラミは太くてカルパスは細い、そんなイメージがあるかもしれません。
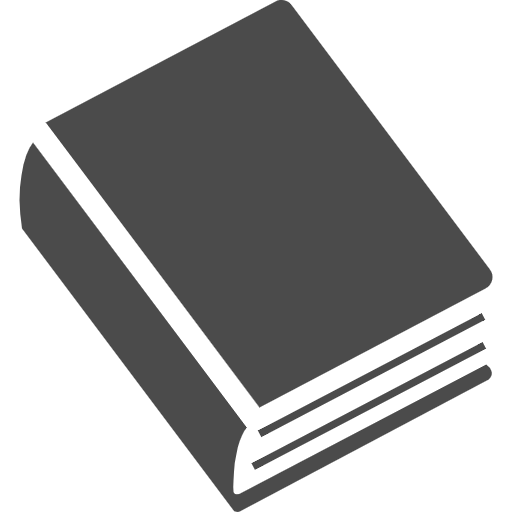
このページを読めば「サラミ」と「カルパス」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
サラミの定義
ドライ‐ソーセージの一種。粗挽きの牛肉や豚肉を調味して腸詰めにし、乾燥させる。サラミ‐ソーセージ。
広辞苑 第七版 1200Pより [発行所:株式会社岩波書店]
続いて「ドライソーセージ」を広辞苑で調べると
乾燥させて水分を少なくし、保存性を高めたソーセージ。
広辞苑 第七版 2124Pより [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、サラミはソーセージを加熱せずに乾燥熟成させた水分量が35%以下の長期保存のきく食べ物であることが分かりました。
牛肉や豚肉の旨みに加えて調味料や香辛料により味がしっかりしているため、ピザのトッピングなどのほか、そのままおつまみとしても美味しく頂けます。

カルパスの定義
カルパスは広辞苑に掲載がないためWikipedia等でリサーチしたところ、元々は細身のドライソーセージの商品名であったことが分かりました。
商標登録がされていないため、今では細く短いドライソーセージが「カルパス」として定着しています。
カルパスの商品の表示にも「ドライソーセージ」の表記があることがありますが、実際には水分が55%以下の「セミドライソーセージ」に分類されます。
カルパスには牛や豚に加えて鶏肉が使われていることが多いため、さっぱりとおやつ感覚で食べられます。

つまり「サラミ」と「カルパス」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- サラミは「牛肉や豚肉が主原料のソーセージを乾燥熟成させたドライソーセージ」
- カルパスは「元々は商品名だが、牛や豚、鶏肉を使用したサラミよりも水分量の多いセミドライソーセージを指す」
となり同じ「乾燥食製品」ではありますが、水分量の違いがあることがわかりました。
また、カルパスは一口サイズのものが多く、サラミに比べてさっぱりと食べられる他、価格も手頃な物が多いためおやつやおつまみとして人気があります。
ハムとベーコン、生ハムとプロシュートの違いについてもまとめています。






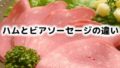
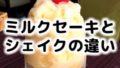
コメント