「能」と「狂言」の違い、あなたは説明できますか?
どちらも日本の伝統芸能ですが、両者に明確な違いはあるのでしょうか。
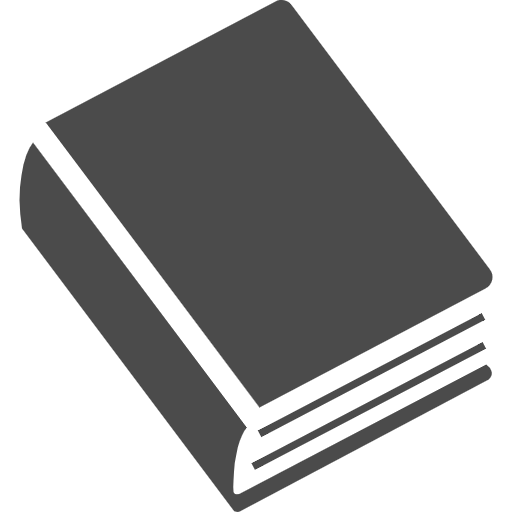
このページを読めば「能」と「狂言」の違いがわかります。
広辞苑より
広辞苑 第七版で各言葉は次のように表現されています。
能の定義
「能」を広辞苑で調べると、
日本芸能の一つで、台詞や歌舞から成る劇。ふつう猿楽の能をさすが、田楽の能もあった。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「能」は歌舞劇で、ジャンルとしてはオペラやミュージカルに近いものであることがわかりました。
もともと「能」は江戸時代までは「猿楽」と呼ばれ、その後、明治時代になると「能楽(のうがく)」の一分野として発展していきました。
「能」は、「能面」をつけて演舞すること、ほとんどセリフがなくすべて音楽や謡(うたい)と呼ばれる声楽で構成されていることが大きな特徴です。
さらに「能」は、2008年(平成20年)にユネスコ無形文化遺産に登録されています。

狂言の定義
「狂言」を広辞苑で調べると、
科白(セリフ)を主体とする劇。歌舞中心の能・踊などに対する。例外に壬生(ミブ)狂言のような無言劇もある。
(ア)能狂言。猿楽の笑いの要素を洗練した科白(セリフ)劇。「おかし」とも。鎌倉・室町時代に主要な芸能となり、能とともに一日の番組に組み入れて演ぜられた。江戸初期に大蔵流・鷺流・和泉流が確立。
(イ)歌舞伎狂言。歌舞伎劇の演目。また、劇そのもの。本来は初期の歌舞伎踊に対して劇的な演目を指した。
広辞苑 第七版 より [発行所:株式会社岩波書店]
とのことで、「狂言」はセリフ劇であり、現在のコントやコメディに近いものであることがわかりました。
狂言も「能」同様に猿楽として発展してきましたが、能と違い、能面はつけないこと、音楽ではなくセリフがメインである事が大きな特徴です。
また、狂言の内容は中世の庶民の日常や説話などを題材にしており、人間の習性や本質を切り取って笑いに変えるというところが面白さの肝であり、人を引き付けるポイントとなっています。

つまり「能」と「狂言」の違いは?
つまりそれぞれの違いは
- 能は「音楽や声楽で表現されるミュージカルやオペラに近い、日本の伝統芸能」
- 狂言は「セリフがメインでコントやコメディに近い、日本の伝統芸能」
となり、能も狂言も、もともとは同じ「能楽」の一分野であることがわかりました。
もともと同じ能楽だったものが、ここまで全く違うジャンルになってしまったことは非常に面白いですね。ちなみに狂言と違い、「能」はセリフがないため、ついつい眠くなってしまいがちですが、能楽師さんによると、「それも楽しみ方の一つ」とのことです。
舞台のマチネとソワレの違いについてもまとめています。




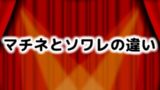
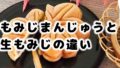

コメント